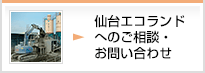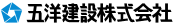���̃y�[�W�́A�z�[��![]() ���ݎ��ށu�V�}���b�T�v�i�Đ����j�̂��ē��̃y�[�W�ł��B
���ݎ��ށu�V�}���b�T�v�i�Đ����j�̂��ē��̃y�[�W�ł��B
���ݎ��ށu�V�}���b�T�v�i�Đ����j�̂��ē�

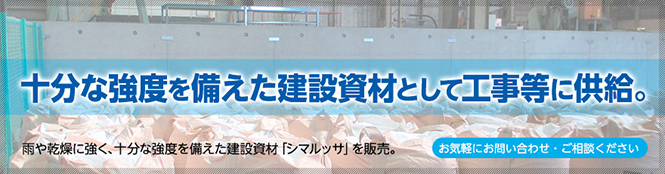
�������B
���݉��D���ʼn��������āA�悭���ߌł܂鍻�A�I���̍Đ����ɉ��ǂ��āA�V�}���b�T�Ƃ��Ĕ̔����A���܂��܂ȓy�؎��ނɊ��p�ł��錚�ݎ��ނł��B
���ݎ��ށw�V�}���b�T�x

���D�ɏ������{�����ƂŁA������Ŏg���錚�ݎ��ށu�V�}���b�T�v�Ƃ��čĐ����܂��B�V�}���b�T�ɉ��H���邱�ƂŐV���ȎR����K�v�Ƃ����A�W���C���b�g�̎��Ɠ��e���̂����ۑS��ړI�Ƃ��Ă���܂��B
���z���ށu�V�}���b�T�v�̔̔�
���܂��܂ȓy�؎��ނɊ��p�ł��錚�ݎ��ށu�V�}���b�T�v��̔����Ă���܂��B
�V�}���b�T�̕i������
| �������� | �i������ | ���l |
|---|---|---|
| �y������ | ���I�� | --- |
| �R�[������ | �R�[���w����800KN/m2 | ��Q�폈���y�ȏ� |
| �����J��Ԃ����� | �����O��ł͍ח������Ȃ� | �J�A�n�������̉e���ɂ��ēD�����Ȃ� |
| ���ߌłߎ��� | �����O��ŗ��q�ׂ͒�Ȃ� | ����ŏ\���]�����\ |
| CBR���� | CBR�l��20���ȏ� | �H�ՍނƂ��ď\���g�p�\ |
| �����Z������ | �e�����Ă��ח������Ȃ� | --- |
| �n�o���� | �y��̉����Ɋւ����������Ă��� | --- |
�y������
���Ǔy�̕����l
���nj�̕����l��\-8�Ɏ����B�\��肷�ׂẲ��Ǔy�ɂ����āA�ח� ����10%�ȉ��ƂȂ��Ă���ח����������ʼn����ꂽ���Ƃ��킩��B���{ ����y�����ނɂ����Ă��V���g�A�S�y����э����y�ł��������̂��A�� �nj�ɂ� �g���h�������́g�I�h�ɐ����ω������Ă��邱�Ƃ��킩��B ���M���ʂ̐��l�����ǑO�ƌ�Ŕ�r����ƁA���M���D�ȊO�ł͉��nj�� ��������X���������Ă���B�\�������ɂ����ă|���}�[�݂̂𐅂ɗn�� ���ċ��M���ʎ������s�����Ƃ���A95%�Ƃ������M���ʂ̌��ʂ��B�� �̂��Ƃ���A���nj�͋��M���ʂ���������ƍl������B���M���D�ł͉� �nj�ɋ��M���ʂ��������Ă��邪�A����͖����Ǔy�ł͌͗t�Ȃǂ����� ���Ă��苭�M���ʂ������Ȃ邪�A���ǂ��邱�Ƃɂ�肠����x�͗t�Ȃ� ����������A���̓y���q�݂̂����M���ʎ����̑ΏۂƂ������߂ɋ��M���ʂ����������ƍl������B pH�ɂ��Ă̓Z�����g�n�ʼn��ނ��g�p���Ă��邽��11�`12���x�ƍ����� ��A���Ǔy�̗��p�ɂ������Ă͕��y�A�~�y�Ȃǂ��s�����Ƃɂ��A���� �A���J���������o���邱�Ƃ�h���悤�ȑK�v�ł���B
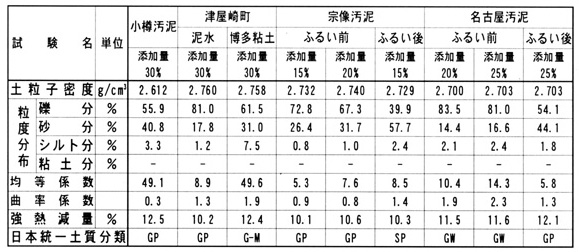 ���Ǔy�̕����l
���Ǔy�̕����l
���ǑO�Ɖ��nj�̗��x���z
���݉��D��{�V�X�e���ɂ����ǂ����ꍇ�́A�����Ǔy�� ���Ǔy�̗��x�ω��ɂ��Č�������B �n�ՍH�w���u�y�̗��x�������@�v�iJGS T 131�j�Ɋ�Â��� �x�������ʂ�}-5�Ɛ}-6�����B�}��葢���ʼn��ɂ��ח����� �������ꗱ�x���z�͗��a�̑傫���E���փX���C�h���A�g���h��g �I�h�̐���ւƕω����Ă���B�܂��A�{�V�X�e���ʼn��ǂ��ꂽ�y �͂ǂ�������l�ȗ��x���z�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��B �ʼn��ނ̓Y���ʂ�15%��20%�ʼn��ǂ����@�����D�����20%��25%�� ���ǂ������É����D�ɂ����āA�Y���ʂ̈Ⴄ���Ǔy�̗��x���z�� ��r����ƁA���̉��D�������ł���ΓY���ʂ��ω����Ă����x���z �̈Ⴂ�͏��������Ƃ��킩��B���̂��Ƃ���A�ʼn��ނ̓Y���ʂ̍� �قɂ�闱�x���z�̕ω��͏��Ȃ��ƌ�����B
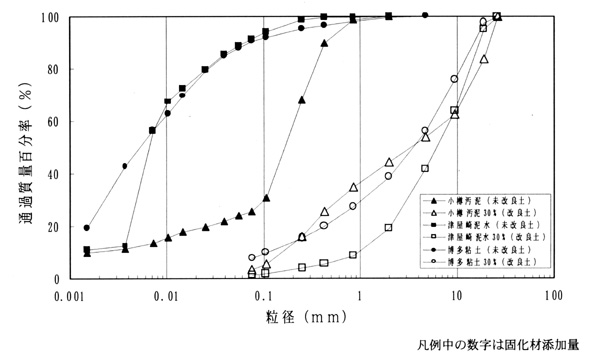 ���ǑO�Ɖ��nj�̗��x���z�i�P�j
���ǑO�Ɖ��nj�̗��x���z�i�P�j
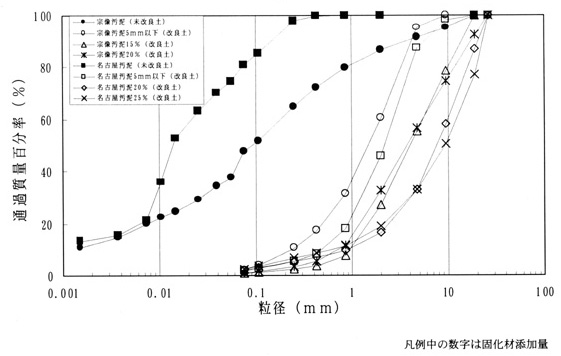 ���ǑO�Ɖ��nj�̗��x���z�i�Q�j
���ǑO�Ɖ��nj�̗��x���z�i�Q�j
�R�[������
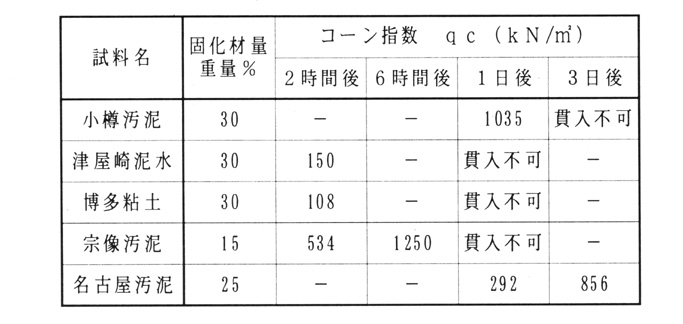
���\�ɉ��nj�̌o�ߎ��ԕʂł̃R�[���w���̕ω��������B ���É����D�ȊO�ł�1����ɂ̓R�[���w����800kN/m2�܂� �͊ѓ��s�ƂȂ��Ă���A1���{����ɒ��ł߂������y�͑�2 �폈���y�Ɣ��f�ł���B���É����D�ł��R���{����ɂ�800kN/ m2���Ă���B�܂��A�@�����D�ł͉��ǂ�2���Ԍ�ɂ͑�3�� �����y�̋��x�������Ă���A�����ɗ��p�\�ł��邱�Ƃ��킩��B
�����J��Ԃ�����
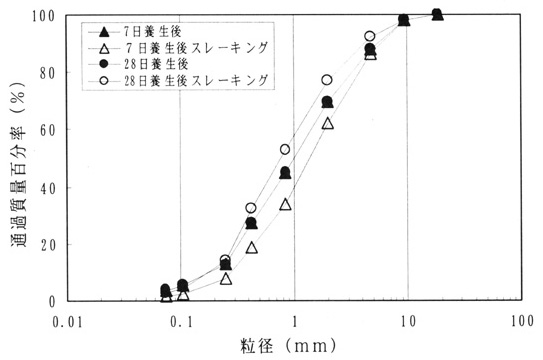
���Ǔy�����R�̉e���������E�������J��Ԃ����Ƃɂ��A�ח������̈��e�����N�����Ȃ����ׂ�B �������@�́A���{���H���c�u�X���[�L���O�������@�v�iKODAN110-1985�j�Ɋ�Â������Ǝ�����24���Ԃ����� ���݂ɍs�������1�T�C�N���Ƃ��āA5�T�C�N�����������Ǒ̗̂��x�������s���X���[�L���O�O�̗��x���z�� ��r�����B �������ʂ�}-8�Ɏ����B�����͏��M���D�̉��Ǒ̂��g�p���A���R�{��7�����28����̉��Ǒ̂��X���[�L���O �����̑O��ŗ��x���肵���B�����O��̗��x���z������ƁA�傫�ȕω��͖����قړ������x���z�ɂȂ��Ă���B ���̂��Ƃ���A���Ǒ̂�p�����n�Ղ��A�J����n�����ʂɂ�鎼����n�Ղ̊������Ă��ח����͋N����� ���ƍl������B�܂��A7�������28���{����̃X���[�L���O�O��̗��x���z�͂Ƃ��ɕω����Ȃ����Ƃ���A7���� �ȏ�̗{�����s���A�����J�Ԃ��ɂ����Ǔy�̐���͕ς��Ȃ����Ƃ��m�F�ł����B
���ߌłߎ���
���łߑO��̗��x����
���Ǔy���{�H���ɒ��ł߂ȂǂŔ�������h���G�l���M�[�ɂ���ė��q�̍ח��� ���N�����Ȃ����ׂ�B
�������@�͉��Ǔy���S���X���[�u�ɓ���A����1.5m���珊��̉Ŏ��R���� �����h������B�h����A�����������F�ɓ��ꗱ�x�������s���h���O�Ɣ�r����B
�����́A�ʒu�G�l���M�[�������ɂ�肷�ׂĎ����ɋz�����ꂽ�Ƃ��Ď��� �ɂ�苁�߂�B�܂��A�����G�l���M�[��Ec=25.3cm�Ekgf/cm3�Ƃ��� �B����́A�n�ՍH�w���u�ˌł߂ɂ��y�̒��łߎ������@�v�iJGS T 711�j����H���E�H�Ղ̒��łߎd���ʂɑΉ����鐔�l�ł���B
Ec=�iWR�~H�~N�j�^V
Ec �F�����G�l���M�[�icm�Ekgf/�p3�j
WR �F�����d�� �ikgf�j
H �F�������� �im�j
N �F������ �i��j
V �F�����̐� �icm3�j
��L�̎���藎���m�����߂�B���l�͈ȉ��̒ʂ�Ƃ���B
Ec =25.3�p�Ekgf/cm3
WR =1.049kgf �i�����S�y�j�E1.009kgf �i����D���j
H =1.5m
V =772.734cm3
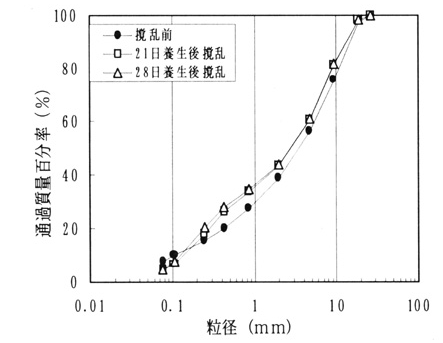 �����D�y���Ǔy�@�G�l���M�[���בO��̗��x���z
�����D�y���Ǔy�@�G�l���M�[���בO��̗��x���z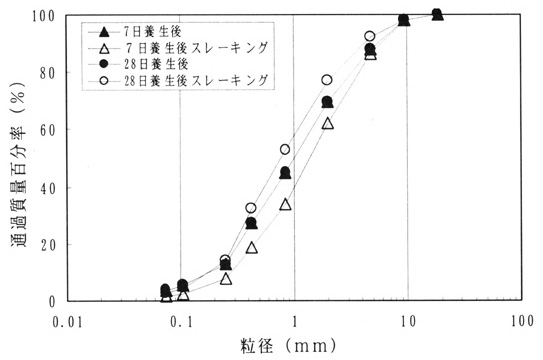 �É���D�����Ǔy�@�G�l���M�[���בO��̗��x���z
�É���D�����Ǔy�@�G�l���M�[���בO��̗��x���z
CBR����
CBR�����͉��\�Ɏ��������̉��Ǔy��p���ĐvCBR�l�����߂��B ���M���D�ȊO�ł�CBR�l��20%�ȏ�������Ă���A���ەܑ������� ������ۂɂ͐vCBR�l��20%���ō��l�ł��邱�Ƃ���A������ ���Ǒ̂͘H���ނƂ��ď\���ɗ��p���\�ł��邱�Ƃ��킩��B�� �M���D�ł�CBR�l��17%�ł���A�ܑ��������������邱�ƂȂǂŘH ���Ƃ��ď\���ɗ��p�\�ł���B �c�����͒É���D���A�����S�y�A�@�����D��0.1%�ȉ��A���M���D ��0.45%�ł���A�ǍD�Ȓn�Ղ̖c������1%�ȉ��Ƃ����K�肩�画�f ���āA���Ǒ̖̂c�������Ⴂ���Ƃ��킩��B���̂��Ƃ��A�{�V�X�e���ɂ����ǒn�Ղ������z���đ̐ϖc�����N�������Ƃ͂Ȃ��Ɣ��f����B
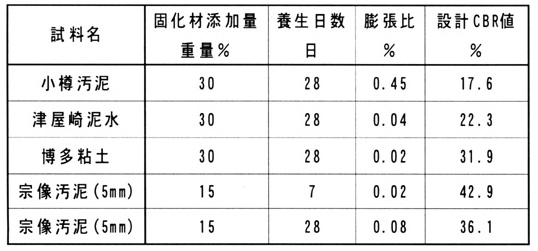 CBR��������
CBR��������
�����Z������
�����Z����p�ɂ��A�{�V�X�e���ō쐬�������Ǔy�̗��x���z�⋭�x�ւ̉e�������邩���m�F���A ����n�ł̉��Ǔy�̎g�p�ɖ�肪�Ȃ����ׂ�B�����Ƃ��Ă͔����S�y�Ɍʼn���30%�Y�������� �����y���g�p�����B �����Z���̍�Ƃ́A���������ǂ������̓���-20���̏�Ԃœ�������24���ԕ��u���A���̌�A+20�� �̏�Ԃ�24���ԕ��u��������Z��������B���̍�Ƃ�1�T�C�N���Ƃ���B�ꎲ���k���x������1�A3�A7�T �C�N����Ɏ������s�����B�܂���r�ΏƂƂ��āA���������������{���������̂��������s�����B �i�ꎲ�����̋����̂̍쐬���@��3-3-3(1)�Ɠ��l�Ƃ���j �\-13�Ɉꎲ���k���x�����̌��ʂ������B�\����P�����{���͗{�������̌o�߂ƂƂ��ɋ��x�� �オ���Ă���̂ɑ��āA�����Z�����1��3�T�C�N���ł͋��x���㏸���Ă�����̂́A3��7�T�C�N�� ���ׂ�Ƌ��x���ቺ���Ă���A�����Z���ɂ��e��������ꂽ�B����́A�Z�����g�n�ʼn��ނ݂̂� ���Ǒ̂̓����Z�������ł����l�̕S�j�����邪�A�������ɋL�ڂ���Ă���悤�Ɏ��ۂ̌���ł� ���Ǒ̂̓}�b�V�u�ȏ�Ԃł���A�e������Ƃ��Ă����Ǒ̕\�ʂ����ŁA���Ǒ̎��g�̑ϋv���ɂ� ���Ȃ��ƍl������B ���ɖ\�I��Ԃ̉��Ǔy�i�������j�������Z���ɂ�藱�q�j�ӂ��N�����Ȃ������m�F���邽�߂ɁA1�A3�T �C�N���̓����Z����ɗ��x�������s���A�����{�����Ԃ̗��x���z�Ɣ�r�����B�}-11�ɓ����Z��O��� ���x���z�������B�}��藱�x���z�ɕω��͌���ꂸ�A�܂����x�����S�ɔ������Ȃ�3���A7���{����ɁA �������������Z���̉e�����čח������Ȃ����Ƃ��킩�����B
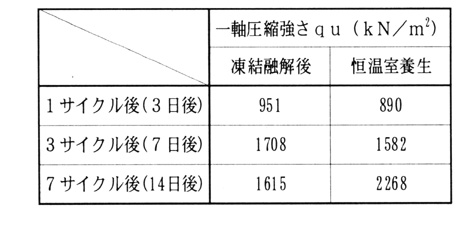 �����Z��O��̈ꎲ���k���x
�����Z��O��̈ꎲ���k���x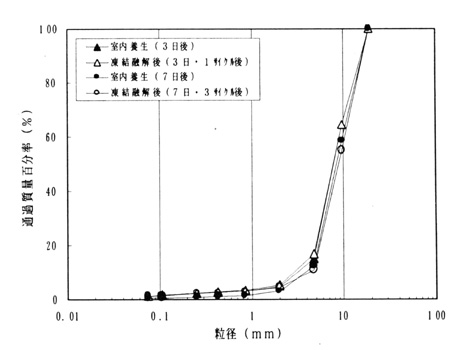 �����Z��O��̗��x���z
�����Z��O��̗��x���z
�n�o�����i����21�N8��6���j
�n�o�����Z�x�v��
| �v�ʂ̍��� | �P�� | �v�ʂ̕��@ | �v�ʂ̌��� | ��l | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | �J�h�~�E�� | mg/l | JIS K 0102 55.4(2008) | 0.001���� | 0.01�ȉ� |
| 2 | �S�V�A�� | mg/l | JIS K 0102 38.1.2�y��38.3(2008) | �s���o | ���o����Ȃ����� |
| 3 | �L�@���� | mg/l | ���a49�N����������64���t�\1 | �s���o | ���o����Ȃ����� |
| 4 | �� | mg/l | JIS K 0102 55.4(2008) | 0.001���� | 0.01�ȉ� |
| 5 | �Z���N���� | mg/l | JIS K 0102 65.2.4(2008) | 0.005���� | 0.05�ȉ� |
| 6 | ��f | mg/l | JIS K 0102 61.2(2008) | 0.002 | 0.01�ȉ� |
| 7 | ������ | mg/l | ���a46�N����������59���t�\1 | 0.0005���� | 0.005�ȉ� |
| 8 | �A���L������ | mg/l | ���a46�N����������59���t�\2 | �s���o | ���o����Ȃ����� |
| 9 | �|�������r�t�F�j��(PCB) | mg/l | ���a46�N����������59���t�\3 | �s���o | ���o����Ȃ����� |
| 10 | �� | mg/kg | ���a47�N�����{�ߑ�66�� | 2���� | �_�p�n�ɂ�����125���� |
| 11 | �W�N�������^�� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.002���� | 0.02�ȉ� |
| 12 | �l�����Y�f | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.0002���� | 0.002�ȉ� |
| 13 | 1,2-�W�N�����G�^�� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.0004���� | 0.004�ȉ� |
| 14 | 1,1-�W�N�����G�`���� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.002���� | 0.02�ȉ� |
| 15 | �V�X-1,2-�W�N�����G�`���� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.004���� | 0.04�ȉ� |
| 16 | 1,1,1-�g���N�����G�^�� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.1���� | 1�ȉ� |
| 17 | 1,1,2-�g���N�����G�^�� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.0006���� | 0.006�ȉ� |
| 18 | �g���N�����G�`���� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.003���� | 0.03�ȉ� |
| 19 | �e�g���N�����G�`���� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.003���� | 0.03�ȉ� |
| 20 | 1,3-�W�N�����v���y�� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.0002���� | 0.002�ȉ� |
| 21 | �`�E���� | mg/l | ���a46�N����������59���t�\4 | 0.0006���� | 0.006�ȉ� |
| 22 | �V�}�W�� | mg/l | ���a46�N����������59���t�\5 | 0.0003���� | 0.003�ȉ� |
| 23 | �`�I�x���J���u | mg/l | ���a46�N����������59���t�\5 | 0.002���� | 0.02�ȉ� |
| 24 | �x���[�� | mg/l | JIS K 0125 5.2(1995) | 0.001���� | 0.01�ȉ� |
| 25 | �Z���� | mg/l | JIS K 0102 67.2(2008) | 0.002 | 0.01�ȉ� |
| 26 | �ӂ��f | mg/l | JIS K 0102 34.1(2008) | 0.3 | 0.8�ȉ� |
| 27 | �ق��f | mg/l | JIS K 0102 47.3(2008) | 0.10 | 1�ȉ� |
�ܗL�ʎ����v��
| �v�ʂ̍��� | �P�� | �v�ʂ̕��@ | �v�ʂ̌��� | ��l | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | �J�h�~�E������т��̉��� | mg/l | JIS K 0102 55.3(2008) | 1.3 | 150 |
| 2 | �Z���N���������� | mg/l | JIS K 0102 65.2.4(2008) | 0.2 | 250 |
| 3 | �V�A�������� | mg/l | JIS K 0102 38.1�y��38.3(2008) | 2���� | 50 |
| 4 | ����y�т��̉����� | mg/l | ���a46�N����������59���t�\1 | 0.02���� | 15 |
| 5 | �Z�����y�т��̉����� | mg/l | JIS K 0102 67.2(2008) | 0.21 | 150 |
| 6 | ���y�т��̉����� | mg/l | JIS K 0102 54.3(2008) | 33 | 150 |
| 7 | ��f�y�т��̉����� | mg/l | JIS K 0102 61.2(2008) | 8.8 | 150 |
| 8 | �ӂ��f�y�т��̉����� | mg/l | JIS K 0102 34.1(2008) | 100 | 4000 |
| 9 | �ق��f�y�т��̉����� | mg/l | JIS K 0102 47.3(2008) | 197 | 4000 |